前へ:No17. 引きこもり次男に起きた体の異変-花火大会で気づいた”心のSOS” | 次へ:No19. 3度目の税務署職員採用試験-父と母、それぞれの思い
外に出ることの負担
花火大会で体調不良になって以来、次男は外出を嫌がり、一日中部屋にこもるようになりました。父親が体調を尋ねても「よくわからん」と答えるばかり。母である私も会話がなく、次男の状態を把握できない日々が続いています。
少しでも体調が改善すればと、私は自宅から通いやすい消化器内科や心療内科をネットでリストアップしました。病院選びは本人に任せたところ、いくつかの候補から心療内科を選びました。家にいる時は普通に見えても、外に出ると強い不安や便意を感じる――父との会話を耳にして、その選択は正しかったのだと納得しました。
通院の現実
これまでに3回通院しましたが、帰宅するとすぐ横になり、そのまま翌日まで寝込んでしまうこともあります。親から見れば「ただ病院に行っただけ」ですが、次男にとっては外に出ること自体が大きな負担なのだと痛感しました。
また初回から薬の服用が始まり、1回目は胃腸の動きをおだやかにする薬、2・3回目は不安や緊張を和らげたり、気分を落ち着かせる薬を処方してもらいました。問題は2回目以降に発生しました。
1日1回就寝前と指示がありましたが、昼夜逆転の生活を送っていたため、いつ寝るのか本人が把握できず、結局半分の薬も飲めませんでした。3回目の薬は2回目と同じものでしたが量が2倍になっており、眠そうな時に飲むようにしたら、微熱・だるさ・関節痛などの症状があらわれはじめました。
副作用かもしれないと気づいた本人は服用をやめ、徐々に症状がよくなってきました。こうして薬ひとつをとっても、生活リズムや体調との折り合いが難しいことを思い知らされます。
記事から得た気づき
先日、ゴールドオンラインで「62歳の母と、無職の35歳息子」の記事を読みました。母は退職後の生活や将来の介護を案じる中で、息子から「母さん、おれ働けないよ」と言われ、出口の見えない不安を抱えていました。
私の場合も息子の年齢が違うだけで、同じ悩みを抱えています。いわゆる“8050問題”が頭から離れず、暗い将来を思い描いてしまうのです。専門家は解決の糸口として、いきなり就職を目指すのではなく、通院や地域の交流会など“小さな社会接点”を増やすことが重要だと指摘していました。
(出典:THE GOLD ONLINE 2025年8月13日配信)
この記事を読み、「社会に出る=働くこと」ではないと気づかされました。人と会話する、誰かと同じ空間にいる――それも立派な社会とのつながりであり、安心感や生きがいを生むのだと。
現実の隔たり
けれども、現実は理想のようにはいきません。次男にとって「引きこもりの会」や「地域の集まり」に参加することは、まだ高すぎるハードルです。外に出て、人と会うだけでエネルギーを使い果たしてしまうからです。
今の次男にとって、唯一の社会との接点は心療内科に通うこと。それがすでに大きな一歩であり、彼にとっては社会との距離を少し埋める行為でもあります。
母として
それでも、心のどこかでは「このままで大丈夫なのだろうか」という焦りが消えません。年齢を重ねれば重ねるほど、息子の未来や私たち親の老いが現実味を帯びてきます。
けれども一方で、病院に行くだけで体調を崩してしまう姿を見ると、無理に社会復帰を迫ることがどれほど酷なことかとも思い知らされます。
「少しずつでも前に進んでほしい」という希望と、「今のままでも仕方ないのかもしれない」というあきらめ。その間で揺れる気持ちを抱えながら過ごす日々です。
先日、次男のひじの内側に絆創膏が貼ってあるのに気づきました。心療内科で血液検査を受けたばかりだったので、つい最悪のことを想像してしまいました。あとで主人から「消化器内科にも行っていた」と聞かされ、ようやく胸をなでおろしました。
その時ふと、ただ隣に息子がいてくれることが、どれほど私の心を救っているのかに気づきました。あの瞬間の絶望を思えば、今の迷いや不安はきっと乗り越えられる――そう思えるようになったのです。
前へ:No17. 引きこもり次男に起きた体の異変-花火大会で気づいた”心のSOS” | 次へ:No19. 3度目の税務署職員採用試験-父と母、それぞれの思い
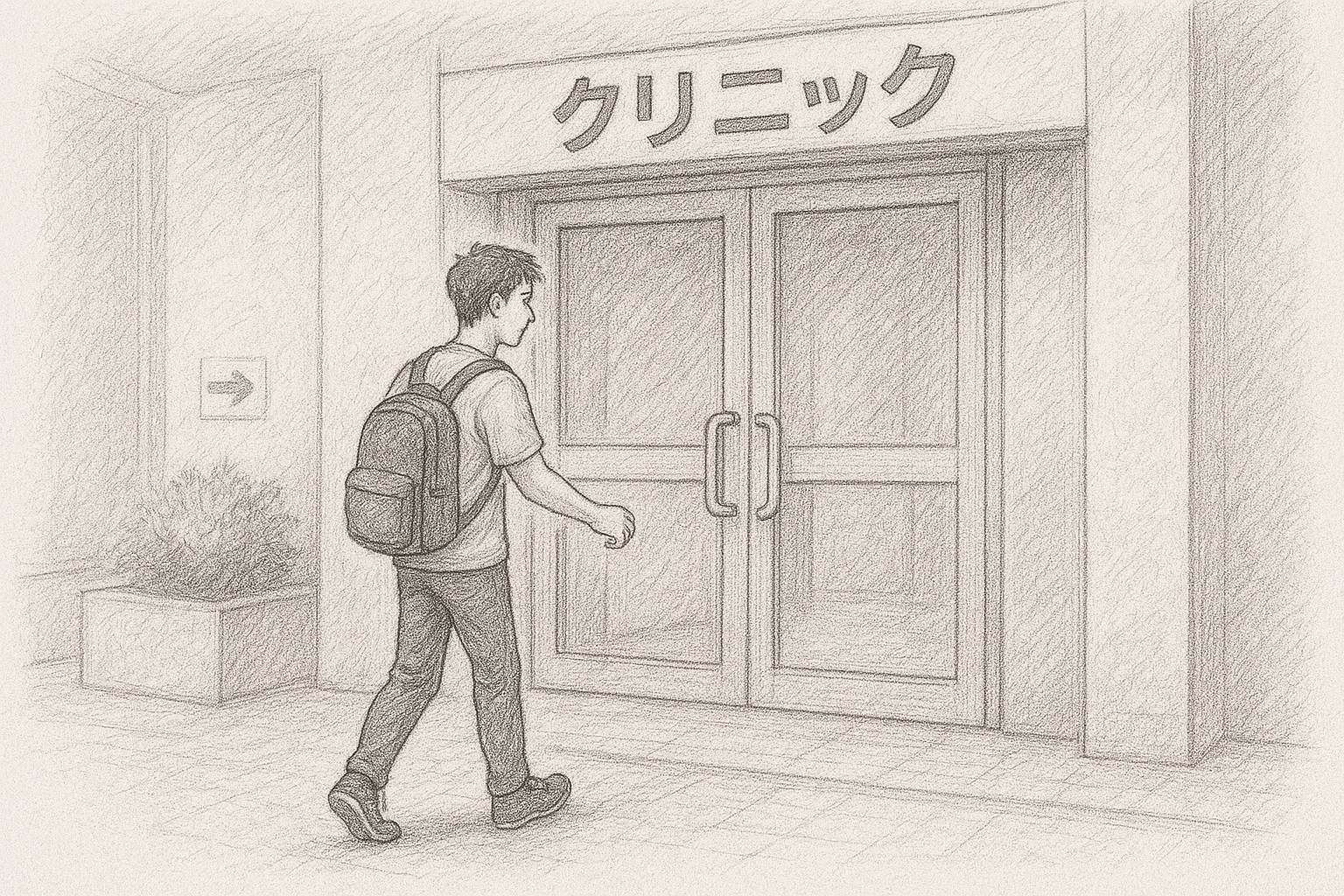

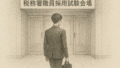
コメント