
前へ:No4. 中学校を卒業してから | 次へ:No6. 社会にふみだそうとして
2024年3月に通信高校を卒業してから、もう3年が経ちました。
「あっという間だった」というより、「まだ3年しか経っていなかった」というのが、正直な気持ちです。
私たち両親は、1年遅れてでも大学に進学してくれたらと願っていましたが、次男には卒業後の進路に対する関心がまったくありませんでした。いつも通り、ゲームをして過ごす日々。本人にとっては、それが自然だったのかもしれません。
進路説明会で先生が「卒業後に何もしないのもひとつの選択」と話していたことを思い出しますが、まさか自分の息子がその道を選ぶとは思ってもみませんでした。
日中、家には私と次男の二人だけ。
次男がいつ起きてくるかわからない中で、私ができたのは、最初のご飯を用意して「母はここにいるよ」と静かに伝えることくらいでした。
彼が部屋にこもっている間、家事以外に私のすべきことはなく、外に働きに出るという選択肢はその頃の私には浮かびませんでした。
実は三男も、小さい頃から学校に行きたがらず、小学校時代はほぼ毎日遅刻。校門まで付き添って登校するのが日常でした。
中学になってからはさすがに付き添いませんでしたが、先生への遅刻連絡が日課のようになり、私は悩み続けていました。
そんな中、次男の不登校も重なり、私はただただ悲しく、今の自分を保つだけで精一杯の日々が続きました。
よく聴いていた人生相談のラジオ番組で、「不登校の原因の一つに家庭の不和がある」と聞いたことがあります。
私たち夫婦は30年前に職場結婚しましたが、価値観の違いから次第に家庭内別居のような状態になっていきました。
価値観のズレのひとつが、子どもとお金のこと。
私の実家は専業農家で、常に誰かが家にいて、子どもを見守るのが当たり前という環境でした。私は、子どもが一人前になるまで母親が寄り添うのが自然だと信じていました。
一方、夫は現代的な考えで、「子どもは保育園に預けて共働きが当然」という立場でした。
私のことを「家で楽をしている」と受け止め、事あるごとに責められるようになりました。
今なら、もう少し相手の立場や言い分にも耳を傾けられたのかもしれません。
けれど、当時の私は精神的に追い詰められていて、自分を守るために相手を攻撃する以外の選択肢を持てませんでした。
そんな夫婦の衝突を目にしていた子どもたちは、どれほど辛かっただろうと思います。
長女はよく、弟たちを別の部屋に連れて行ってくれていました。
子どもと向き合ってきたつもりでしたが、次男が心の奥で何かに苦しんでいたことに、私は気づけませんでした。
知らず知らずのうちに、深い傷を負わせてしまったことは、否定できない事実です。
「あの時ああしていれば」「もっとこうすべきだったのでは」と今でも思うことはあります。
でも、その答えはいまだに見つかっていません。

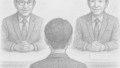
コメント